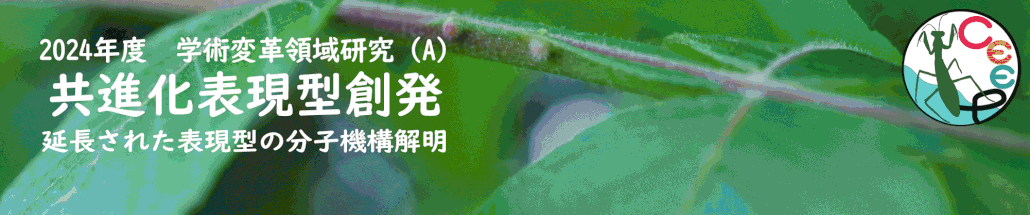プロジェクト
A01 行動操作

計画研究 A01-1
ウイルスによる宿主行動操作の分子機構解明
研究代表者:勝間 進(東京大学)
研究分担者:疋田 弘之(京都大学化学研究所)
バキュロウイルスはチョウ目昆虫に感染する大型の二本鎖DNAウイルスである。バキュロウイルスに感染した昆虫は、感染末期になると行動が活発になり、寄主植物の上方に移動する。これは、100年以上前から知られている「Wipfelkrankheit (梢頭病)」と呼ばれる現象であり、ウイルスが自身の伝播範囲を広げるために行う利己的な行動操作であると考えられている。私たちは、順遺伝学、および逆遺伝学的な手法を用いて、この「延長された表現型」の分子機構解明に取り組み、ウイルスゲノムにコードされる「行動制御」遺伝子候補の同定に成功した。それらの機能解析から、ウイルスが昆虫の脳・中枢神経系に対して適切な時期に、適切な量で感染することが、ウイルスによる「行動制御」に必要であることが示唆されている。一方、感染昆虫の「行動実行」に関わる宿主因子の機能解析には至っていない。本研究では、ウイルスによる「行動制御」と感染宿主の「行動実行」のメカニズムに迫ることで、ウイルスが宿主の行動を操作する分子基盤を解明する。

計画研究 A01-2
寄生虫による宿主行動操作の分子機構解明
研究代表者:佐藤 拓哉(京都大学)
研究分担者:三品 達平(九州大学農学研究院)
研究分担者:岩谷 靖(近畿大学工学部)
研究分担者:入谷 亮介(理化学研究所)
研究分担者:佐倉 緑(神戸大学大学院理学研究科)
ハリガネムシ類は、森林や草原で暮らす宿主(カマキリや直翅類等)の体内で成虫になると、自らが繁殖をする水辺に戻るために、宿主を操って入水させる。私たちは、この奇異な行動操作において、宿主の活動量の上昇により水辺遭遇確率が高まる可能性と水面から特異的に反射される水平偏光への正の走性強化が重要な役割を果たすことを明らかにした。しかし、その分子機構は未だ謎に包まれている。本研究では、(1)行動操作候補遺伝子群とエフェクター分子の探索・同定を進め、さらに(2)宿主のシグナルカスケードへの介入メカニズムを理解する。これらにより、ハリガネムシ類が宿主の入水行動を生起する分子機構の解明に迫る。

計画研究 A01-3
トキソプラズマ原虫による宿主行動操作の分子機構解明
研究代表者:西川 義文(帯広畜産大学)
研究分担者:潮 奈々子(帯広畜産大学)
トキソプラズマは哺乳類や鳥類を中間宿主とし、ネコを終宿主とする偏性細胞内寄生原虫である。本原虫は中間宿主の脳や筋肉にシストを形成し、慢性感染する。近年の研究により、本原虫の慢性感染はげっ歯類の行動変容やヒトの精神・神経疾患の発症リスクを高めることが報告され、動物やヒトの神経機能に様々な影響を及ぼすことが報告されている。我々はマウスを用いた動物行動学、感染病理学的な手法を用いて、トキソプラズの感染活動期には宿主免疫反応が関与するうつ様症状の発現、感染慢性期には中枢神経系の神経伝達物質の変調による記憶能力の低下を明らかにしている。これらの解析から、宿主動物の中枢神経系がトキソプラズマ由来のエフェクター分子により影響を受けることが推測されるが、その分子の同定には至っていない。本研究では、トキソプラズマのエフェクター分子が宿主の行動を操作する分子基盤を解明する。

公募研究 A01-K1-1
植物による昆虫行動操作の分子神経機構
研究代表者:木矢 剛智(金沢大学)
昆虫は自由意思によって好みの花を訪れる一方、植物は昆虫の好みの蜜や匂いを用意することで花粉の運搬を昆虫に依存し、時には共進化をすると考えられてきた。私たちはこれまでの研究より、「昆虫の訪花行動が植物から操作されている」新規な現象を見出してきた。これは、植物が昆虫に依存する関係とは逆に、植物が昆虫の行動を操作する機構を進化的に獲得してきた可能性を示すものである。本研究では、昆虫体内に取り込まれた植物の花粉がエンドビオントとして働き、脳機能に作用することで昆虫の行動操作が生じる、といった仮説の検証と分子神経機構の解明を行う。

公募研究 A01-K1-2
狂犬病ウイルス感染が誘発する宿主攻撃行動のメカニズム解明
研究代表者:正谷 達謄(岐阜大学)
研究分担者:内藤 清惟(鹿児島大学)
狂犬病ウイルスは感染すると、宿主の中枢神経系で増殖しその情動を大きく変化させ、目の前の動物に対して咬みつくといった攻撃行動を誘発する。同時に唾液腺からのウイルス分泌も亢進するため、これにより咬傷を介した他個体への伝播が可能となる。すなわち狂犬病ウイルスは、他の個体へ伝播するために、宿主の情動を大きく変容させるとともに生理的機能も改変するユニークな戦略に基づいて現世まで存続してきたと考えられる。本研究では、「活性化神経細胞のみが一過性に蛍光を発するトランスジェニックマウス」と「狂犬病ウイルスの遺伝子操作系」を組み合わせ、イメージング、マウス行動実験およびマウス遺伝子工学を駆使し、ウイルスが扁桃体の神経異常を誘発することで宿主の情動・生理を操作する機構を明らかにする。さらに、ウイルスおよびマウスの遺伝子工学技術を応用することで、ウイルス側の因子「エフェクター蛋白質」の同定にも挑む。

公募研究 A01-K1-3
エンドビオントが操るオスの攻撃性
研究代表者:堀 亜紀(金沢大学)
オス同士の「攻撃行動」は動物界に広く観察される本能的行動であり、種の存続から社会性構築まで、生物にとって重要な役割を果たしている。我々はこれまでに、ショウジョウバエの共生細菌である乳酸菌がオスの攻撃行動を抑制することを発見した。そこで本研究では、ショウジョウバエの攻撃行動を乳酸菌が操作するメカニズムの解明を目指す。そのため、乳酸菌の変異株を用いた遺伝学的解析を実施し、攻撃行動抑制に関与する乳酸菌のエフェクター分子を同定する。さらに、乳酸菌が操作する宿主の神経系基盤を明らかにする。本研究は、共生細菌が宿主の中枢神経系をコントロールし、延長された表現型を発現させるプロセスの解明に貢献する。
A02 生殖操作

計画研究 A02-4
細胞内共生体による昆虫の性操作-その多様性と機能の基盤解明
研究代表者:陰山 大輔(農研機構)
研究分担者:大鷲 友多(農研機構)
研究分担者:林 正幸(農研機構)
多くの昆虫の細胞内には、母から子に綿々と世代を越えて伝わる様々な共生体が存在している。父から子には伝わることができないこれら共生体の中には、宿主の生殖や性決定をコントロールし、メスのみしてしまうものが存在する。これまでに多岐にわたる細菌やウイルスなどの細胞内共生体が様々な昆虫の性を操作していることが分かってきたが、原因遺伝子やメカニズムの一端については数個の系でしか明らかになっていない。我々は、これまでに、チョウ目昆虫に共生する細菌ボルバキアが宿主に起こすオス殺しメカニズムの背景に、性決定遺伝子カスケードの操作があること、また、それが培養細胞レベルで再現できることを明らかにした。本計画では、以下の2項目を実施することにより、多様な性操作の共通性と進化的起源を探る。①チョウ目昆虫、ショウジョウバエ、クサカゲロウや昆虫培養細胞を用いて、細胞内共生体が起こす宿主操作を解析する。②様々な昆虫種から共生ウイルスおよびそれらが持つ宿主操作候補遺伝子を探索し、昆虫や細胞を用いて機能解析を行う。

計画研究 A02-5
昆虫共生体による性操作-その多彩な分子基盤の解明
研究代表者:春本 敏之(筑波大学)
昆虫に共生する微生物には、オスだけを殺すなど、宿主昆虫の生殖を勝手に操作してしまうものの存在が知られている。この生殖操作は、昆虫と微生物という異なる生物種が相互作用することで初めて顕現する、延長された表現型のひとつとしてとらえることができる。本研究では、非モデル昆虫における手付かずの生殖操作現象を研究対象に据える。昆虫と共生微生物の組み合せに応じて、モデル昆虫に用意された高度な分子レベルの実験手法を転用する、あるいは、当該非モデル昆虫にゲノム編集・遺伝子組換え技術を本格適用することで、生殖操作機構の全容解明を目指す。

公募研究 A02-K1-4
性決定遺伝子型と性操作型共生体の不和合により築かれる生殖防壁の存在証明
研究代表者:鈴木 雅京(東京大学)
生物間で普遍的なプロセスに関わるメカニズムやその責任遺伝子には強固な保存性がみられる、というのが生物学の常識である。ところが、雄と雌という二つの性はあらゆる多細胞生物において普遍的にみられるにも関わらず、性決定プロセスには驚異的な多様性がみられる。有性生殖の根幹に関わるプロセスになぜ多様性が生じるのか、この理由を説明するため、本研究課題では宿主の性を操作する性操作型の共生細菌に着目する。我々は特定の地域に生息するマイマイガ集団からオス殺し型に属するスピロプラズマを同定した。一方で、マイマイガの雄化と雌化に関わる性決定遺伝子を同定し、それらに亜種間多型があることを突き止めた。興味深いことに、性決定遺伝子型が異なる亜種間交雑を行うと、次世代において性転換、雌致死、間性が出現することを発見した。野外でも特定の地域において同様の現象が起きていることもわかってきた。そこで本研究では、性操作型の共生細菌が性決定遺伝子の多様化を促す要因となり得るか検証すると共に、その適応的意義や生態学的意義を明らかにする。

公募研究 A02-K1-5
寄生性甲殻類による宿主甲殻類に対する性操作機構の種間比較
研究代表者:豊田 賢治(広島大学)
フクロムシは甲殻類への寄生に特化した寄生性フジツボであり、宿主であるカニやヤドカリから栄養を収奪し、宿主自身の繁殖能力を喪失させ(寄生去勢)、宿主がオスの場合は形態や行動をメス化させる(擬似メス化)。我々はこの擬似メス化現象に着目して、沿岸性普通種のイワガニやホンヤドカリ類に高頻度で寄生しているフクロムシ類を研究モデルとし、ゲノム解読や合成生物学、そして生理学実験からフクロムシが引き起こす擬似メス化の分子基盤を明らかにする。
研究協力者:梶本麻未(神奈川大学総合理学研究所)

公募研究 A02-K1-6
細胞内共生細菌による特殊なRNA高次構造を介した宿主操作
研究代表者:大手 学(東京慈恵会医科大学)
昆虫の共生細菌であるボルバキアは、宿主にウイルス抵抗性を付与することが知られている。この効果により、ボルバキアを保有するネッタイシマカでは、デングウイルスなどの病原体の媒介が抑制される。本研究では、この細菌の共生によって誘発される抗ウイルス機構の引き金となる現象の詳細を明らかにする。宿主昆虫と共生細菌の双方に由来する因子が協調してウイルス由来分子に変化を誘導し、新たな表現型が獲得される仕組みを理解する。ショウジョウバエと昆虫ウイルスを用いた実験系からモデルを構築し、さらにこれをヤブカ–病原性ウイルス系に適用することで、普遍的な機構の解明を目指す。
A03 形態操作

計画研究 A03-6
昆虫による植物形態操作および花形成誘導の機構解明
研究代表者:沓掛 磨也子(産総研)
研究分担者:植松 圭吾(慶應義塾大学)
虫こぶは、昆虫が植物の形や性質を自分に都合の良いように改変し、その結果生じた特殊な構造物であり、昆虫にとって巣であり食物供給源である。虫こぶの形態は、興味深いことに、それをつくる昆虫によって多種多様であるが、同じ昆虫がつくる虫こぶは、形が厳密に決まっている。つまり虫こぶは、昆虫側の遺伝子発現の結果が植物上に現れた「延長された表現型」であり、昆虫が植物の発生プログラムに介入し、操作することで作り出した植物の形態なのである。しかしながら、どのような昆虫由来因子が植物組織の発生や生理状態を改変し、通常では見られない精妙な虫こぶ形態をどのように再現的に作りあげているかという問いについては、まだ十分な答えが得られていない。本研究では、この謎に迫るべく、エゴノキにバナナ房状の虫こぶを形成するエゴノネコアシアブラムシを対象に研究を推進する。本種虫こぶの大きな特徴は、形成に失敗した虫こぶから、異常な形態をした花が通常より遅れて咲く、「遅れ花」という現象である。本研究では、この独自モデル系を用いて、虫こぶ形成過程における花器官分化関連遺伝子の詳細な分子発生学的解析を行い、アブラムシによる花の器官形成メカニズムを利用した虫こぶ形成の分子基盤について、昆虫・植物の両面から具体的に明らかにしたい。

計画研究 A03-7
モデル植物実験系を駆使した昆虫による植物形態操作の分子機構解明
研究代表者:平野 朋子(京都府立大学)
研究分担者:佐藤 雅彦(京都府立大学)
研究代表者らは近年、「昆虫が、植物の幹細胞、二次細胞壁、および維管束の形成を誘導し、花器官・果実形成遺伝子を利用して、虫こぶを形成する」ことを証明した。そして、これらの遺伝子は、昆虫から分泌されるCAPペプチドと植物側受容体CAPRによる反応から誘導されることを突き止め、完全に人工的な虫こぶの再構築に成功した。すなわち,虫こぶ形成は,「本来、植物の内在性のCAPペプチドがCAPRに作用して起こる植物の形態形成の制御システム」を、昆虫がハイジャックした結果であることがわかった。そこで,本研究では,形態操作の本体である「CAP-CAPRの操作」の分子機構を網羅的に明らかにする。

公募研究 A03-K1-7
線虫による植物形態操作の分子機構解明
研究代表者:澤 進一郎(熊本大学)
本研究は、植物寄生性線虫が植物の形態や生理を操作する分子機構を解明することを目的としている。研究対象として、サツマイモネコブセンチュウをモデルとし、シロイヌナズナやトマトへの感染実験を通じて寄生機構を解析する。
本研究では、CLEペプチドとその受容体であるCLV1との相互作用を解析し、地下部の線虫感染が地上部の花成に及ぼすシグナル伝達経路を明らかにする。また、線虫による根瘤形成と他の寄生生物(ヌルデシロアブラムシなど)による虫瘤形成の分子機構を比較し、寄主植物の形態変化に共通するメカニズムを解明する。さらに、我々は、線虫のすりつぶし液をシロイヌナズナの根に塗布すると根瘤が形成されることを見いだしており、RNAseq解析を用いてこの瘤形成の遺伝子発現プロファイルの解析も行う。本研究の成果は、寄生生物による宿主操作の分子基盤を明らかにし、寄生の進化や生物間相互作用の理解を深めることに貢献すると考えている。

公募研究 A03-K1-8
昆虫ー細菌共生系が産生する「虫こぶ誘導因子」の実体解明
研究代表者:土'田 努(富山大学)
昆虫による虫こぶ形成は、生物学の様々な分野から注目される現象であるが、実験室内での操作が困難なことから、機構の多くは未解明である。我々は、「植物に寄生する植物」アメリカネナシカズラに寄生して虫こぶを形成する、という極めて興味深い生態をもつマダラケシツブゾウムシを実験室で安定して維持する系を確立し、虫こぶ形成機構を明らかにすべく研究を進めている。我々は、本種ゾウムシの全ての個体からSodalis属の共生細菌を見出し、虫こぶ形成にも重要な役割を担っていることを示唆する結果を得た。本課題では、この植物―寄生植物―昆虫―共生細菌から成る“超入れ子型共生系”を研究対象として、本種ゾウムシによる虫こぶ形成因子を同定することを目的とする。

公募研究 A03-K1-10
病原細菌による植物の花芽形成阻害機構の解明
研究代表者:岩渕 望(東京大学)
植物病原体は植物に多様な病徴を引き起こし、農作物の収量や品質を著しく低下させる。中でも、植物の形態変化を伴う劇的な病徴については、様々な病原体で研究が進められてきた。しかし、これまで分子機構が解明されているものは、イネばか苗病のジベレリンの例のように、植物ホルモンが関与する事例が多くを占め、エフェクターが関わる事例はまだ解明が進んでいない。花は顕花植物において、有性生殖を通じた生存戦略、遺伝的多様性の創出、および病原体の排除に重要な表現型である。さらに、人類にとっては農業生産の基盤であり、文化的・経済的にも極めて重要な意義を持つため、古来より人々の関心を集めてきた。しかし、病原体の感染によって花の表現型が大きく変化することがある。特に、絶対寄生性の植物病原細菌であるファイトプラズマは、きわめて特異な現象を引き起こす。通常の花芽形成を阻害し、植物の生育ステージを生殖成長から栄養成長へと「巻き戻す」のである。しかし、この驚くべき現象の分子機構と生物学的意義は、依然として未解明である。本研究では、ファイトプラズマのエフェクターの中から、花芽の形成を阻害し、生殖成長から栄養成長へのステージ転換を引き起こす因子を探索するとともに、植物病原体による生殖阻害がもたらす生物学的意義を包括的に理解することを目指す。
A04 発生操作

計画研究 A04-8
飼い殺し型寄生蜂の毒による巧みな発生操作の分子基盤
研究代表者:丹羽 隆介(筑波大学)
研究分担者:島田 裕子(筑波大学)
研究分担者:上山 拓己(筑波大学)
寄生蜂は、宿主(寄主とも呼ぶ)に一度に数百種類にも及ぶ毒を注入し、その作用によって、宿主の特定の組織の退縮や免疫応答の抑制しつつ、一定の期間は宿主を生かした後で宿主を殺して乗っ取る「飼い殺し(koinobiont)」を実現させる。こうした宿主の発生過程や表現型の巧みな操作の理解には、寄生蜂毒の実態と宿主に対する近接的作用の分子メカニズムを明らかにする必要があるが、それらは多くの部分で不明である。また、それぞれの寄生蜂は特有の宿主特異性を有し、生態学的・進化学的に古くから多くの研究者の関心を惹いてきたが、寄生蜂種ごとの宿主/非宿主の別を毒と毒の作用の多様性から理解することも大きく立ち遅れている。本研究では、Drosophila属ショウジョウバエを宿主とするAsobara属寄生蜂を主な研究対象として、寄生蜂毒による巧みな宿主発生操作の分子基盤の解明を目指す。

公募研究 A04-K1-11
ネジレバネによる宿主イネウンカ類の生殖・形態発生操作の分子基盤の解明
研究代表者:吉田 一貴(農業・食品産業技術総合研究機構)
ネジレバネはネジレバネ目という600種あまりの小さなグループを構成する寄生性の完全変態昆虫である。多様な昆虫を宿主として利用するネジレバネは、昆虫の中で唯一の寄生者parasite(≠捕食寄生者parasitoid)であり、宿主昆虫に対し生殖能力の喪失(去勢)や寿命の延長、行動の変化といった操作を行うことが知られている。ときに稲作に大きな被害をもたらす害虫イネウンカ類にもネジレバネが寄生するが、ネジレバネに寄生されたウンカでは、雌雄ともに外部生殖器が劇的に変形し中性的な外見となる現象、すなわち「間性化」が起こる。この現象はネジレバネの中でも特異なものであり、ウンカ科の昆虫を宿主とするネジレバネでしか見られない。本研究ではネジレバネ-ウンカの系を用いて、分子基盤をはじめとする「間性化」という現象の全容を解明する。また宿主操作の表現型が異なる他のネジレバネ-宿主系、さらには他の寄生性昆虫との比較により、操作に関わる因子の普遍性・非普遍性を見出すことで、ネジレバネの寄生性や宿主操作の進化の過程の理解を目指す。
A05 共生表現型変容

計画研究 A05-9
共生細菌による宿主表現型変容の分子基盤の解明
研究代表者:深津 武馬(産総研)
研究分担者:森山 実(産総研)
研究分担者:古賀 隆一(産総研)
研究分担者:二橋 亮(産総研)
研究分担者:二河 成男(放送大学)
近接的な生物間相互作用による表現型変容としての「延長された表現型」は、これまでもっぱら「寄生」的な関係において論じられてきた。ところが「相利」的な共生関係では、対抗進化というよりはむしろ協調進化の帰結として表現型変容が生じてきたはずである。本計画研究では、生存に必須な共生細菌が宿主の外見や行動に適応的な変容をもたらすカメムシ腸内共生系をモデルとして、その分子機構を解明する。具体的には、①保護色である緑の体色が共生細菌と宿主カメムシの相互作用で形成される共生体色変容、および②生存に必須な共生細菌を垂直伝達するための宿主昆虫の行動が両者の相互作用で制御される共生行動変容に関わるメカニズムの解明に取り組む。寄生関係における「対抗的な表現型操作」と相利関係における「協調的な表現形変容」の分子機構の比較解析により、生物間相互作用における表現型共進化の本質の理解をめざす。

公募研究 A05-K1-12
ペプチドホルモンの模倣を介した植物と菌類の共生関係成立の分子機構の解明
研究代表者:古水 千尋(島根大学)
陸上植物の80%以上はアーバスキュラー菌根菌(AM菌)との共生により土壌からの無機塩類の取り込みを高めている。このAM菌のエフェクター候補として、植物ペプチドホルモンの一種CLEに類似したCLE様ペプチド(AM-CLE)が報告されているが、AM-CLEの役割は解明されていない。本研究では、多様な真菌類におけるCLE様ペプチドの探索と、遺伝的冗長性の低いコケ植物(写真:ゼニゴケ、本研究でも使用)を用いた分子遺伝学的解析を組み合わせることで、AM-CLEの起源と植物との共生関係における機能と作用機構の解明に取り組む。これにより、生物間の相互作用を制御するエフェクターとして、宿主の生理活性分子を模倣する分子が進化する分子基盤を理解するための基礎を築くことを目指す。

©CEEP, Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (A)